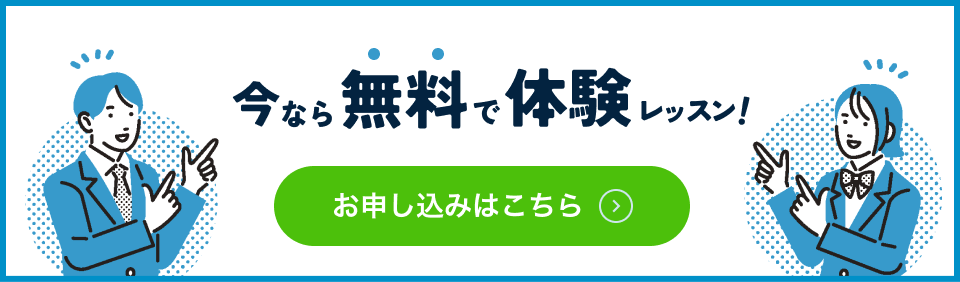私立医学部志望者に送る:共通テストは果たして必要か?
1.私立医学部志望者必見!共通テスト利用入試の概要
共通テスト利用入試は、私立医学部において共通テストの成績を利用して入試を行う方式です。
これにより、受験生は複数の大学に出願する際に、共通テストの成績を活用することができます。
私立医学部の入試は多様化しており、共通テストを利用することで、受験の幅が広がるメリットがあります。
特に、私立医学部専願の受験生にとっては、上手く利用することは戦略的な選択肢となるでしょう。
ただ、「医学部志望者誰にでも進められる医学部入試」というわけではありません。
共通テスト利用入試とは?その基本を知ろう
共通テスト利用入試は、私立大学が共通テストの成績を基に選抜を行う方式です。
受験生は共通テストを受験することで、複数の私立医学部に出願することが可能です。
これにより、受験生は一度の試験で複数の大学にアプローチできるため、効率的な受験が実現します。
多くの場合、学力試験は共通テストの結果を利用し大学独自の学力試験は課されません。
私立医学部の共通テスト利用のメリット
私立医学部における共通テスト利用入試のメリットは多岐にわたります。
まず、医学部受験の幅が広がることが挙げられます。
私立医学部一般選抜は試験日が連続するので多くの大学を受けることは難しのですが、共通テストの成績を利用する共通テスト利用入試に出願することで、合格のチャンスが増えます。
また、共通テストは非常に多くの受験生が参加するため、自己採点結果を見て受験生は自分の学力を客観的に評価することができます。
さらに、私立医学部専願者にとっては共通テストの英語、数学、理科で受けられる大学もあるため効率的な学習が可能です。
私立医学部の共通テスト利用入試のデメリット
私立医学部共通テスト利用入試にはメリットもありますが、デメリットもあります。
共通テストの問題は独特なものも多く、「共通テスト対策」は欠かせません。
私立医学部一般選抜対策に時間を使いたいのですが、共通テストを受けるのであれば共通テスト対策にも時間を割く必要があります。
国公立医学部を併願する受験生は問題ないのですが、私立専願の受験生にとっては私立医学部一般選抜対策と共通テスト対策のどちらも中途半端に終わってしまう恐れがあります。
次に、私立医学部共通テスト利用入試のボーダーライン得点率が非常に高いことが挙げられます。
駿台予備学校のデータによれば日本医科大学91.1%、順天堂大学医学部90.6%、帝京大学医学部90.0%と、私立医学部共通テスト利用入試のボーダーライン得点率が90%を超える大学もあります。駿台予備学校では私立医学部共通テスト利用入試で最もボーダーラインの低い大学を埼玉医科大学の80.6%としており、合格するためには少なくとも80%を超える得点率が必要です。
国公立医学部でも島根大学医学部79.5%、香川大学医学部79.3%など、共通テストのボーダーライン得点率が80%を下回る大学もあり、私立医学部のハードルの高さが分かります。
2026年度の私立医学部入試における変化
2026年度の私立医学部入試では、北里大学医学部が共通テスト利用入試後期を実施するなど共通テスト利用の選抜方式がさらに拡大します。
これに伴い、各大学のボーダーラインも変化する可能性があります。
受験生は、最新の情報を常にチェックし、戦略を練る必要があります。
また、共通テストの成績が重視されるため、受験生は早期からの共通テスト対策が求められます。
2.共通テスト利用入試は果たして必要か?
共通テスト利用入試が本当に必要かどうかは、受験生の状況や志望校によって異なります。
駿台予備学校や河合塾の「私立医学部共通テスト利用入試のボーダーライン得点率」を見て、「自分はそこに届きそうなのか」を考えて下さい。
一般的には、共通テスト利用入試のボーダーライン得点率を取れそうな受験生は私立医学部一般選抜でも複数の合格を得ることが出来そうです。
私立医学部受験で、「合格ラインぎりぎり」あるいは「合格は簡単ではない」という受験生は共通テスト対策に時間を使うことなく、一般選抜対策に時間を使った方がいいと思います。
共通テストを受けることで得られるメリットとデメリットをしっかりと理解し、自分に合った受験戦略を立てることが重要です。
その際には、「合否判定に使われる科目」も考えて下さい。
私立医学部専願者には国語や地歴公民をやっている時間は無いでしょう。
合格最低点の理解:2026年度の私立医学部
2026年度の私立医学部共通テスト利用入試におけるボーダーライン得点率は、共通テストの難易度に影響されます。
また各大学の合格最低点は、受験生の成績や志願者数によって変動します。
駿台予備学校・ベネッセや河合塾が行う、共通テストの自己採点集計と予想ボーダーライン得点率を参考にするといいでしょう。
知恵袋から学ぶ共通テスト利用の実態
受験生の間での共通テスト利用に関する情報は、知恵袋などの掲示板で多く共有されています。
実際の受験生の体験談やアドバイスを参考にすることで、共通テスト利用の実態を把握することができます。
特に、成功した受験生の戦略や失敗談は、今後の受験に役立つ貴重な情報です。
受験生は、こうした情報を積極的に活用し、自分の受験戦略に反映させることが求められます。
一方で、そういった情報の全てが正しいというわけではありません。
情報の取捨選択を心掛けてください。
3.私立医学部の入試方式と受験科目
私立医学部の入試方式は多様であり、共通テスト利用入試もその一つです。
特に、共通テストを利用する場合、受験科目の選択が合否に大きく影響します。
受験生は、志望校の入試科目と配点そして2次試験の内容をしっかりと把握し、計画的に学習を進める必要があります。
共通テストにおける受験科目の選択肢
共通テストでは、受験科目の選択肢が豊富です。
私立医学部を志望する場合、一般的には英語、数学、理科(物理・化学・生物)はどの大学でも求められます。
共通テスト利用入試では、国際医療福祉大学医学部や順天堂大学医学部のように英語、数学、理科の他に国語と地歴公民も必要な大学があります。
受験生は、自分の得意科目や志望校の要求に応じて、受験科目を選ぶことが重要です。
また、英語にリスニングが必要なのかも確認してください。
3教科での受験はどうか?—ボーダーラインの動向
英語、数学、理科の3教科での受験は、私立医学部入試において一般的です。
共通テスト利用入試でも、英語、数学、理科の3教科の受験で構わない大学を選択することで負担は大きく減少します。
私立専願の受験生が共通テスト利用入試を考えるのであれば、3教科で受験できる大学に絞って考えるといいでしょう。
併願の選択肢とその戦略
私立医学部を志望する受験生にとって、併願の選択肢は非常に重要です。
共通テストを利用することで複数の大学に出願できるため、共通テスト利用入試を利用した併願戦略を立てることが可能です。
受験生は、志望校の試験科目やボーダーライン、2次試験の内容を考慮し、併願校を選定することが重要です。
この時に帝京大学医学部や近畿大学医学部後期のように、合否判定に使われる科目が特殊な場合もありますので、正確な医学部入試情報を把握してください。
4.共通テスト対策:成功のカギ
共通テスト対策は、私立医学部共通テスト利用入試において成功するための重要な要素です。
受験生は計画的な学習を行い、共通テストの形式や出題傾向を理解することが求められます。
特に、過去問題の活用や模試の受験は、実践的な対策として非常に効果的です。
受験生は、これらの対策を通じて、自信を持って試験に臨むことができるでしょう。
直前の準備と重要な注意点
試験直前の準備は、受験生にとって非常に重要な時期です。
この時期には、過去問題の復習や模試の結果をもとにした最終調整が求められます。
また、体調管理やメンタル面のケアも重要です。
受験生は、リラックスしながらも集中力を保つための工夫を行い、試験に臨む準備を整えることが必要です。
私立医学部一般選抜に向けた準備も必要で、共通テストと私立医学部一般選抜のバランスには注意が必要です。
国公立医学部併願の場合は、ここにさらに国公立2次試験対策も加わりますので綿密な時間管理が欠かせません。
効果的な過去問題の活用法
過去問題の活用は、共通テスト対策において非常に効果的です。
受験生は過去問題を解くことで、出題傾向や問題形式を理解することができます。
また、解答後には必ず復習を行い、間違えた問題の理解を深めることが重要です。
合わせて、時間の使い方を学ぶことも重要です。
過去問題を繰り返し解くことで、自信を持って試験に臨むことができると思います。。
受験生が知るべき出願期間とスケジュール
受験生にとって、出願期間やスケジュールの把握は非常に重要です。
私立医学部の出願期間は大学によって異なるため、各大学の公式サイトを確認することが必要です。
私立医学部共通テスト利用入試には前期と後期があります。
前期と後期では出願期間が異なります。
特に後期は共通テストの自己採点結果を考えて出願出来ますので、より効果的な出願が出来ます。
出願書類の準備や受験料の支払いなど、スケジュール管理をしっかり行うことで、スムーズな受験が可能になります。
出願と試験の日程管理の重要性
出願と試験の日程管理は、受験生にとって非常に重要です。
受験生は、出願日や試験日をカレンダーに記入し、スケジュールをしっかりと管理することが求められます。
また、試験前の準備や体調管理も重要な要素です。
日程管理を徹底することで、受験生は安心して試験に臨むことができるでしょう。
ここのところは家族の協力があると受験生の負担は減ります。
5.国公立と私立大学の比較
国公立大学と私立大学の選択は、受験生にとって重要な選択肢です。
私立医学部は、入試方式や学費が国公立大学医学部とは異なります。
受験生は、自分の志望や学力に応じて、どちらの大学を選ぶべきかを慎重に考える必要があります。
また、併願戦略を立てる際にも、国公立と私立の特性を理解することが重要です。
国公立医学部との併願戦略
国公立医学部との併願戦略は、受験生にとって非常に重要です。
国公立大学医学部を受験するためには共通テストの受験は必須で、国語と地歴公民の受験も求められます。
一方で、私立医学部受験では共通テスト利用入試を除けば共通テストの受験は必要ありません。
また、国公立医学部2次試験の問題や試験時間と私立医学部一般選抜の問題、試験時間とは大きな違いがあります。
併願するとなると両方ヘの準備が必要となり、受験生の負担は大きくなります。
受験生は、自分の学力や志望校の特性を考慮し、国公立と私立の併願をするのかを考える必要があります。
私立医学部入試の特徴
私立医学部入試は、国公立大学とは異なる特徴があります。
国公立大学医学部入試では共通テストをまず受けて、さらに各大学の2次試験に臨みます。
2次試験の問題は単科大学を除き、理系学部共通問題になりますので「クセ」の無い問題となります。
一方、私立大学医学部では総合大学であっても、医学部と他学部の受験生の質が大きく異なることから、「医学部独自問題」を使用しますので、大学ごとの特徴がはっきりと出ます。
また、私立大学医学部は「一般的に試験時間が短い」という特徴があり、単に解けるだけでなく「早く正確に解く」ことが要求されます。
国公立2次試験のように「難しい問題を、時間を掛けてじっくり解く」のとは大きな違いがあります。
私立医学部受験では、各大学の出題傾向を理解することが重要です。
私立医学部志望者が考えるべき進学の選択肢
これまで見てきたように、私立医学部入試と国公立医学部入試では大きな違いがあります。
医学部志望者は自分の学力や置かれた状況を考えて、「私立専願で行くのか国公立併願で行くのか、国公立専願で行くのか」を考えることが大切です。
併せて、私立医学部の共通テスト利用入試に出願するのかを考えて下さい。
6.まとめ:共通テストは本当にいらないのか?
共通テストの必要性については、受験生の状況や志望校によって異なります。
医学部を志望する受験生の皆さんは、共通テストを受けることで得られるメリットとデメリットをしっかりと理解し、自分に合った受験戦略を立てることが重要です。
私立医学部受験だけを考えている受験生の皆さんは、自分の合格可能性を高めるのは「私立医学部一般選抜対策に集中」なのか、「共通テスト対策も行う」のかをしっかりと考えて下さい。
なお、共通テスト利用入試には出願しないものの、「最後の模擬試験」、「本番入試に慣れる」という意味で共通テストを受けることも「アリ」です。